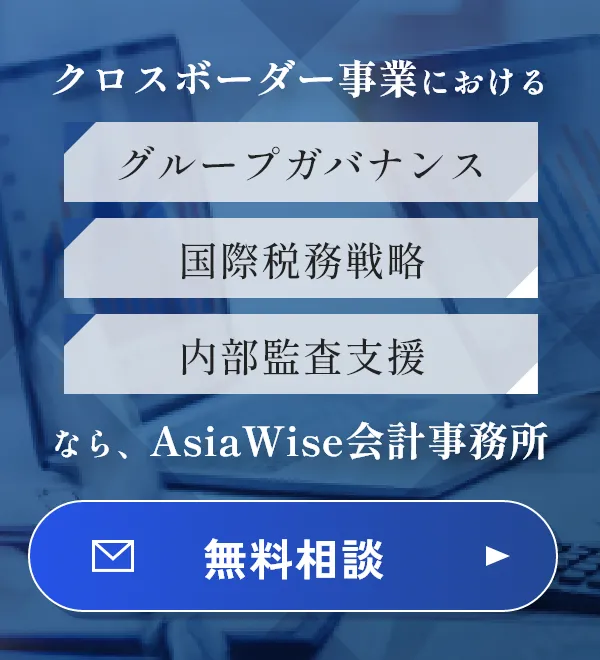「見えなくなった」中国子会社
中国の経済環境は近年、大きな構造的変化を遂げています。従来の「世界の工場」としての地位を維持しつつ、内需主導型の成長へと転換が進んでいます。2020年以降、新型コロナウイルスの影響により多くの企業が中国への出張や現地監査を一時的に中断せざるを得ない状況となりました。この間、オンライン会議やリモート対応は急速に浸透したものの、現地での対面によって得られる「現場感覚」やリスク兆候への感度が損なわれたとの指摘もあります。
更に現在では、中国の情報管理規制の強化により、ノートパソコンやスマートフォンなどの情報端末の持ち込みに制約が生じており、監査対象から中国拠点を外す企業も増えています。筆者自身も、コロナ前は毎月のように中国に渡航し、現地法人の内部監査を担当していましたが、コロナ後はその頻度が著しく減少しています。
その一方で、中国における事業環境は急速に変化しており、現地駐在員の努力に支えられながらも、リスクの実態はかつてとは大きく異なっていることが想定されます。こうした現地が見えない、風通しの悪い状況下では、企業のガバナンスやコンプライアンスに深刻な課題が潜んでいるかもしれません。
本シリーズでは、筆者が中国子会社に対する監査で直面した課題や論点について、実例を交えてご紹介していきます。
中国における重要論点:PE課税リスク
政府の権限が強い中国において、事業運営と税務リスクは切っても切り離せません。税務リスクに適切に対応しない場合、多額の追徴課税を受けたり、二重課税が発生したり、グループ全体の税務戦略にゆがみが生じる可能性があります。特に、日本本社等からのサービス提供が継続的に行われるケース等では、中国側でPE(Permanent Establishment:恒久的施設)と認定され、中国で企業所得税が課されることになります。中国でのPE認定を受けたとしても、日本側での課税は残りますので、結果として国際的二重課税に陥ることになり、その解消を行うことが困難な状況となってしまいます。
こうした課税リスクに対して適切な対応を怠れば、グループ全体の税効率が毀損することになります。経営・財務の健全性を維持するためには、日本、中国双方の租税法制、日中租税条約に基づき実務的なリスク管理が極めて重要です。PE認定という観点からは、出張者の滞在日数管理や契約スキームの適正化、移転価格税制対応など、事前に講じるべき措置は多岐にわたります。
監査の視点:関係会社間債権債務への対応
海外子会社との取引において、関係会社間の債権債務は「連結上で相殺される」「相手がグループ内企業である」といった理由から、監査上の優先度が下がることがしばしばあります。しかし、これらの債権債務が長期にわたり未回収となる場合、以下のような実務的なリスクが発生する可能性があります:
- 外貨規制の影響で送金が認められない/遅延する
- いわゆる「PE課税」により、現地法人に追加的な課税が行われる
具体的な事例としては:
- 現地法人負担の出向者立替給与の未払金を計上しているものの、外貨規制上の登録などが適切に実施できておらず長期間滞留している
- 現地法人からの送金に際して、中国所得税税が控除されている(「みなしPE」課税が発生している可能性)。
監査上、以下の観点での確認が重要です:
- 関係会社間債権債務の滞留管理を行っているか
- 長期滞留している債権・債務が残存していないか
- 中国子会社から本社への送金にはどの様な類型があるか
- 送金に際し、非合理な法人所得税が課されていないか(「みなしPE課税」)
とくにPE課税のリスクについては、中国拠点を対象とする監査において必須の確認、検討項目です。この点に関し、筆者の旧知である矢野綾香税理士の了承を得て、同氏がまとめた中国PE課税に関する連載記事をご紹介させて頂きます。
PDF:中国・インド 日系企業が直面する国際的な人材活用とその実践的課題 第6回(最終回) サービスPEを中心とした中国PE課税の実務
AsiaWise会計事務所による支援
中国子会社の可視性が下がる中で、従来の管理体制では対応しきれていないリスクが潜在している可能性があります。AsiaWise会計事務所では、中国子会社に対する内部監査経験を豊富に有するメンバーが、現地の規制や商習慣を踏まえた実践的な支援を提供します。